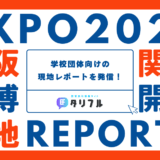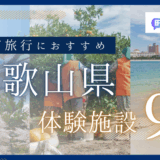公益社団法人全国修学旅行研究協会では、毎年「関東地区」「東海地区」「近畿地区」を対象に、『修学旅行の実施状況調査』を実施されています。
2024(令和6年)度の修学旅行の実施調査概要
▼調査時期:(2024年/令和6年)7月~(2024年/令和6年)12月
▼調査対象:以下3つの地区の公立中学校
| 関東 | 東海 | 近畿 | 合計 | |
| 調査校数 | 1,290 | 624 | 1,144 | 3,058 |
| 回答校数 | 1,290 | 624 | 1,102 | 3,016 |
| 回答率(%) | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 98.6 |
| 集計対象校数 | 1,290 | 624 | 1,102 | 3,016 |
本調査は、本年2025年に17年目を迎えられ、毎年、回答を寄せてくれる学校数は約3,000校とのこと。
この学校数は、全国の公立中学校数の約3分の1にあたり、極めて信頼性の高い数値や内容が記載されているといえます。
また、回収率はここ数年、調査対象校の96%以上を維持しており、本年度においては98.6%を達成されました。
★参照元:調査・研究報告|修学旅行ドットコム (shugakuryoko.com)
修学旅行実施について課題に感じること3選

今回は、2024(令和6年)度の修学旅行の実施調査より、「修学旅行実施に当たっての意見」という質問項目に着目をしました!
全国の先生が抱える「修学旅行実施における課題」とは一体どんな内容なのでしょうか?
本記事では、その課題の中から3つ抜粋しまとめましたので、是非最後までご覧ください♪
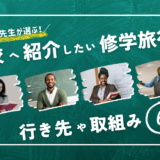 【関西編】学校の先生が選ぶ!他校へ紹介したい修学旅行の行先や取り組み6選│京都でおすすめの体験学習や班別行動の実例をご紹介
【関西編】学校の先生が選ぶ!他校へ紹介したい修学旅行の行先や取り組み6選│京都でおすすめの体験学習や班別行動の実例をご紹介
(1)オーバーツーリズム問題

「オーバーツーリズム」とは、観光地に人が集まり過ぎて渋滞が起きたり、街にゴミが散乱するなどのマナー違反が相次いだりと、観光が地域の生活に負の影響を及ぼす現象のことを指します。
特に京都にみられる有名観光地への「オーバーツーリズム」は、修学旅行実施上の大きな課題になっています。
先生の実際の声(悩み)
- 訪日外国人観光客等の影響もあり、公共交通機関を利用しての移動が予定通りいかず、行程に支障をきたしている。
- 旅行客の増加で、各所渋滞が起こり目的地に辿り着けない。新幹線への乗り遅れ等も考えられる。
- インバウンド需要により、価格が高騰しているだけでなく、宿泊先の確保が困難になっている。
- 海外からの旅行者の増加により、訪問先(特にUSJ、京都市内施設)のトラブル(予定していた路線バスに乗車できない、混雑で予定時間内に見学できない等)が多発している。
課題ごとの解決策と提案
- 「地域周遊型」への見直し:宿泊地周辺で体験活動を組み、移動距離を減らす
- 観光地の「代替地」提案:京都市内→近隣(大原、宇治、滋賀の比叡山など)
- 混雑データを活用した計画:Google混雑予報や観光地のリアルタイム情報を活用
- 新たな宿泊地の開拓:都市部から郊外・地方(例:福知山、亀岡、大津、近江八幡など)へ
- オフシーズン・平日利用の促進:宿泊費抑制+空室確保
- 地域との事前連携による“枠取り”:自治体や観光協会との連携で団体枠を確保しやすく
- 地域分散型修学旅行の推進:混雑地域以外の魅力的なコンテンツ開拓(例:農村体験、自然体験)
- デジタルツールの活用:事前学習で学びを深め、現地での見学時間を補完
問題を乗り越えるには?
関西方面への修学旅行はやはり「京都」が人気ですが、隣の「滋賀」にも素敵な観光素材がたくさんあります。
滋賀県には、世界遺産にも登録されている「比叡山延暦寺」や、大河ドラマで今注目を集めておる「石山寺」があります。
また、日本一大きな琵琶湖を活かした「自然体験学習」や、「信楽焼」などの陶芸体験もできたりと、まさに教育旅行の聖地といえるでしょう。
都市部観光ではなく、「地域課題×探究型学習」や「SDGs体験」などの地域連携型の新たな教育旅行モデルの開発や、修学旅行における公共交通優先枠の導入、価格抑制の支援制度など、国や自治体への政策的要望が必要になると考えます。
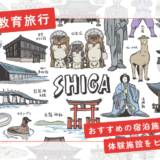 【教育旅行向け】滋賀の宿泊施設・見学・体験施設をまとめました
【教育旅行向け】滋賀の宿泊施設・見学・体験施設をまとめました
(2)旅行費用について

圧倒的に関西方面中心の関東、東西多方面に分散している東海、航空機利用が多い近畿、という3地区それぞれの特色はありますが、あらゆるものの値上がりにより、1人当たりの旅行費用は高騰しています。
次に、旅行費用に関する先生の実際の声について、みていきたいと思います。
先生の実際の声(悩み)
- 費用の高騰が著しい(特に貸切バス)
- 保護者の過重な負担軽減のため、様々な工夫を強いられており、従来の修学旅行が出来なくなってきている。
- 旅行費用の高騰は、実施方法や行き先の変更も含め検討しなければならないところまできている。
- 費用の高騰にあたり、就学支援金の限度額も考慮すると、目的地や体験活動の範囲が限られてくる。
- 物価や交通費の値上がりと修学旅行費上限額が釣り合っておらず、行き先やプログラムが限られてしまう。
課題ごとの解決策と提案
- 行程の見直しで移動距離を最小化
→ 例:広域移動を避け、宿泊地周辺に観光や体験を集中させる「定点型」旅行
- 「近場×体験型」の旅行へのシフト
→ 長距離移動より、地元や近隣でのSDGs体験・地域交流活動など - 「分散型修学旅行」モデル
→ 学年を分けて小規模グループで旅行することで、柔軟な日程とコスト削減を実現 - 修学旅行の目的を再定義
→ 「観光」から「キャリア教育」や「防災・地域理解」など目的に応じた再設計
- 自治体・観光地の教育旅行助成を積極活用
→ 教育旅行誘致を積極的に行っている都道府県の補助制度を利用する - 「教育目的に特化した受け入れ施設」の活用
→ 公的施設・自然体験スクール・自治体直営の体験施設など、コストを抑えながら学びも深められる
問題を乗り越えるには?
修学旅行の本質を「観光」から「地域体験・学び」へと転換し、近隣地域での探究型プログラムや公的支援・寄付を活用した資金多様化を進めることが、持続可能な実施への鍵といえます。
地域・行政・保護者と連携しながら、共創型の新しい修学旅行モデルを構築する必要がありそうです。
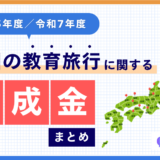 【2025年度・最新版】令和7年度「教育旅行」に関する全国の助成金情報まとめ!
【2025年度・最新版】令和7年度「教育旅行」に関する全国の助成金情報まとめ!
(3)先生の働き方改革について

教員の働き方改革が進む中で、修学旅行の在り方にも見直しが求められています。
現場の声から見えてきた課題と、これからの持続可能な取り組みについて、具体的に見ていきましょう。
先生の実際の声(悩み)
- 仕事としての参加であるにもかかわらず、実費負担が非常に高い。やりがいだけではやっていけない仕事の一つとなっている。
- 夜間の巡視、保護者から要求される過剰なサービスなど、教員の負担感はずいぶん前から限界を超えている。
- 配慮を要する生徒が年々増えており、それに対応する職員等の人員配置が必要となっている。
- 働き方改革が進む中、修学旅行引率者の勤務等について配慮されるべきである。
- 修学旅行の実施の有無から検討する時代に入ってきている。旅行中の教職員への負担が大きい割に、教育的効果は大きくないと感じる。
課題ごとの解決策と提案
- 外部人材の活用(「教育旅行サポーター」など)
→ 学校OB・地域ボランティア・民間団体・元教員などの協力者を旅行に同行(例:食物アレルギーや障害対応に専門スタッフを配置) - ナイトスタッフ・ナーススタッフの配置
→ 夜間巡回や体調対応の一部を外部人材に依頼(コスト増には助成活用)
- 「個別支援が必要な生徒」への専門職同行
→ 特別支援教育支援員や看護師、スクールカウンセラーなどの同行制度化 - 少人数班やバディ制度の活用
→ 教員だけでなく、生徒同士が支え合う仕組みづくりもリスク軽減になる
- 引率教員への手当・出張旅費の適正支給
→ 実費補填+宿泊・夜間勤務などに応じた手当制度の拡充を教育委員会に要望 - 時間外労働の把握と代休・振替制度の徹底
→ 修学旅行=「特別勤務」扱いとし、出張後の休養確保を義務化(勤務管理の見直し) - 引率希望制・ローテーション制の導入
→ すべての教員が毎年引率ではなく、希望や適性に応じて割り当てを調整
- 旅行を「事前・事後学習」と連動させる探究型に変える
→ テーマ設定・振り返り・レポート制作・発表会などを通じて教育成果を見える化 - 教員の役割=引率者ではなく「学びのファシリテーター」へ転換
→ 体験先での振り返り指導、観察記録などに集中し、“教育者”としての意義を回復 - ICTや動画記録による省力化と共有化
→ 行程管理・記録・評価をデジタルで効率化し、教員の負担を減らす
 教育旅行に使える!おもしろツール3選│教育旅行担当者におすすめのアプリや商材をご紹介
教育旅行に使える!おもしろツール3選│教育旅行担当者におすすめのアプリや商材をご紹介
問題を乗り越えるには?
先生方の実際の声から、修学旅行が教員の過重労働の象徴になってしまっている現実が伝わってきます。
修学旅行自体を「なくす」のではなく、本来の教育的価値を守りながら、教員の負担を軽減するという方向での持続可能な仕組みが必要であると考えます。
教員の過重負担を見直し、外部人材との役割分担・制度的手当の整備によって、学びの質を保ちながら持続可能な修学旅行を実現することが急務です。
まとめ│学校の先生が選ぶ!修学旅行実施について課題に感じること
いかがでしたでしょうか?
修学旅行は、子どもたちの学びと成長に欠かせない大切な教育機会です。
一方で、修学旅行を取り巻く環境は大きく変化しており、これまで通りの実施が難しくなっています。
費用や安全管理、教員の負担といった課題に対し、学校・旅行会社・地域が連携して柔軟に対応していくことが求められています。
持続可能な修学旅行の形を模索しながらも、生徒たちが安心して学びを深められる体験の場を守っていく取り組みが、今こそ重要です。
-2.png)